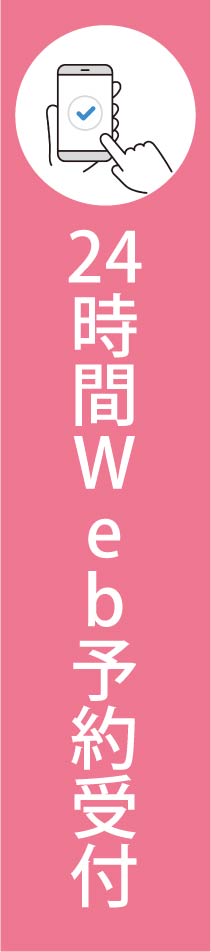中期中絶手術(現在休止中)
中期中絶手術(妊娠12〜21週6日まで)
2024年1月より受入れを一時的に休止しております。再開のめどが立ちましたらHPでお知らせいたします。
妊娠12週から妊娠21週6日までの中絶手術は、12週未満に比べてリスクが高く、週ごとにリスクが増していきますので早めの受診をお勧めいたします。
手術は、子宮口を開く処置(子宮頚管拡張)を行い、十分に子宮口が開いてから子宮収縮剤を投与し人工的に陣痛を引き起こし流産させる方法で行います。子宮口を十分に拡張する時間は妊娠週数、体質(子宮頸管の硬さ)などにより個人差があり、数日かかることもあります。
流産の痛みを少なくし、子宮頸管裂傷、子宮破裂などの合併症のリスクを減らすために、子宮頚管拡張を十分に行う必要があり、また、身体に負担がかかるため数日の入院が必要です。

保険者の出産育児一時金は母体保護を目的としており、分娩の事実に基づいて支給されます。中期中絶の場合も保険者への申請により出産育児一時金(48.8万円)が支給されます。必要な書類は当院で準備いたしますので、窓口でご相談ください。また、初期中絶と異なり処置後に死産届・埋葬許可証が必要になります。
中期中絶手術の費用について
患者様負担額(税込)
| 妊娠週数 | 入院日数 | 出産育児一時金医療機関直接払制度 | |
| 利用の場合 | 利用しない場合 | ||
| 12週0日~19週6日 | 3泊4日〜 | 50,000円〜 | 538,000円〜 |
| 20週0日~21週6日 | 3泊4日~ | 100,000円~ | 588,000円~ |
※患者様負担額には、初診料、検査費、手術費、埋蔵料(6.6万~6.9万)、入院費、術後診察費など全ての価格を含みます。
※初診時に30,000円(税込)の保証金をお支払いいただき、残金を手術時にお支払いいただきます。保証金は手術を受けない場合でも返金いたしません。
※頸管拡張不良で胎児娩出まで追加で1日処置に要した場合は、1日分の入院費28,160円(税込)が必要となります。
※入院した後に中期中絶手術をキャンセルする場合は、通常の入院費用を頂いております。
※出産一時金の医療機関直接払制度とは・・・妊娠された方がご加入されている医療保険者に、当院が代わりに出産育児一時金(家族出産一時金、共済の出産費および家族出産費を含む)48.8万円を請求し、退院時の清算の際に48.8万円を費用から控除する制度です。
※退院時の清算には、クレジットカードがご利用できます。
検査、処置内容
| 検査・処置内容 | |
| 初診日 説明 術前検査 |
医師による説明 超音波検査 HIV検査 B型・C型肝炎検査 梅毒検査 血液型検査 貧血検査 |
| 入院、手術 | 子宮頸管拡張 静脈全身麻酔 超音波検査 手術 |
| 術後診察 術後検査 |
超音波エコー |
中期中絶手術をご希望の方の
予約から手術・検診までの流れ(中期中絶手術)
予約方法
- STEP1.予約
電話(042-535-3544)もしくはWEB予約システムで診察のご予約をお取りください。WEB予約システムは24時間、診察券のない方も予約可能です。
当院は、予約のない方の受診もできますので、予約なしで来院いただいても結構です(診察は予約の方優先となります)。
WEB予約
診察当日の流れ
- STEP2.受付
受付し、問診表記入を行います。当日は健康保険証をお持ちください。
- STEP3.診察
妊娠検査、超音波エコー、問診を行い正確な妊娠週数を確定させます。
- STEP4.手術手続き、手術前検査
手術が決まりましたら、諸手続きを済ませ、手術日、手術を説明を受け、採血を行います。
- STEP5.清算
受付で清算を行います。
入院日
- STEP6.入院日
午前8:30に受付で入院手続きいただきます。料金を前払いいただきます(退院時に清算いたします)。クレジットカードでの支払い(一括)が可能ですが、中期中絶は支払額が大きいのでお気を付けください。入院期間前半は、子宮頚管拡張の処置をいたします。
- STEP7.手術日
子宮口が十分に開大しているのを確認後、LDR室で点滴より子宮収縮剤を投与し、人工的に流産を起こし中絶術を行います。中絶術後は、回復室で休息後、病室でお休みいただきます。
- STEP8.退院日
手術日翌日に、医師の診察を受け医学的な問題がなく、体調がよろしければ、ご家族に死産届けを役所で提出頂き、埋葬許可が下り次第退院となります。
- STEP9.清算
受付にて清算いただきます(通常、入院予定日数より1泊多めにお支払いいただいております)。
退院後
- STEP10.術後検査
出血の有無、子宮内の遺残物の有無を超音波エコーや内診により診察いたします。術後に2,3回検査が必要になります。術後のピル処方や避妊リング装着などについても遠慮なくご相談ください。
- 母体保護法14条により、中絶手術を受ける場合は、既婚・未婚に関係なく、男性側の同意が必要になります。初診日にお渡しする同意書に必要事項を記載、捺印頂き、手術当日にご提出ください。
- 未成年の方の場合は、保護者の署名が必要になります。男性側が未成年の場合は、男性側の保護者にも同意書に署名を頂かなければなりません。